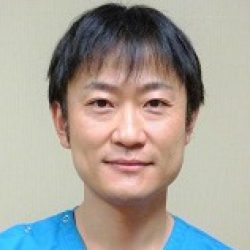今日の午後は以下の手術を行いました。
・加齢性下眼瞼内反症(逆さまつ毛)1件
・翼状片手術 1件
・白内障手術 11件
・網膜硝子体手術(茎離断) 3件
(黄斑前膜2件、網膜中心静脈閉塞に伴う黄斑浮腫1件)
まずまずの症例ですが、17時前には終わってしまいました。手術の準備や移動などがとてもスムーズで、スタッフに感謝です。ありがとう。
今日は早めに帰って、子供の相手もできました。
色覚異常? 病態
網膜の中の視細胞に光が届いて、物が見えるときに、錐体という視細胞が色を判別するのに役立つことを、色覚異常?にて記載しました。
赤色によく反応するL-錐体、緑色によく反応するM-錐体、青色によく反応するS-錐体の3種類が、それぞれ光に反応し脳へと信号を送ります。そして、3つの錐体から届けられた情報を脳が再合成して、色を再現するのです。
色覚異常?で光の3原色について書きましたが、

例えば、緑の光が目に入ると、M-錐体が主に反応し、脳に信号を送ります。
黄色の光が入った時には、L-錐体とM-錐体が主に働き、脳に信号を送るのですが、脳ではこの2つの信号を再合成して黄色と判断します。
強い白い光を見たときは、L-錐体、M-錐体、S-錐体の全てが強く反応するのです。
(一般の方が分かりやすいかな?というレベルで書いています。専門的に表現が異なることはご理解下さい。)
色覚異常とは、この3つの錐体のどれかに異常があり、ある色の光への反応がなくなってしまったり、鈍くなってしまうことを言います。
ある錐体が全く機能しないものを色盲、反応が弱いが、ある程度は機能するものを色弱と呼びます。
実は、最近の正式な学会などでは、色盲や色弱という呼び方はされなくなり、
1つの錐体が全く機能しない場合に、残りの2種類の錐体で読み取ることから2色覚(以前の色盲)。
1つの錐体が正常には機能せず、反応が弱いながらも、一応は3種類の錐体が機能している場合に、異常3色覚(以前の色弱)。
と呼ばれるようになっています。
また、専門的ですが、
赤に反応するL-錐体の異常⇒1型
緑に反応するM-錐体の異常⇒2型
青に反応するS-錐体の異常⇒3型などという分類もあり、
上記の分類とあわせて、例えば赤に反応する錐体が全く機能しない場合には、1型2色覚、少しは機能する場合を1型異常3色覚というように呼びます。
と、ここまで書いてみましたが、自分で読み返してみても、眼科医とかではない皆様に呼んで頂いても、全く分からないのでは??と、ちょっと冷や汗をかいています。困ったな・・・・。
赤・緑・青を感知する錐体のどれに異常があっても、色覚異常になるわけですが、赤だけの場合、赤と緑の場合、青だけの場合、全ての錐体が駄目な場合(杆体1色覚:全色盲)など、様々な組み合わせがあり、組み合わせの種類によって、「どのような見え方になるのか、視力がまずまずなのか、視力も悪いのか。」症状は様々なのですが、全ては書ききれないし、逆に分かりにくくなってしまいそうです。
実は色覚異常をお持ちの方の大多数は、1型色覚(L-錐体の異常)、2型色覚(M-錐体の異常)の2つになるので、今後は、この2つについて書いて行くことにしますね。
先天的なL-錐体の異常とM-錐体の異常をまとめて、先天赤緑色覚異常と呼びますが、一般的に先天色覚異常といえば、この赤緑異常のことを言います。
(先天性の杆体1色覚:全色盲などは数万人に1人の病気で、僕の人生ではまだ担当したことがないくらい稀な病気です。)
色覚のこと、ちょっと書こうと思ったのですが、なんだか大変な分野です・・・。もう何回かに分割して書いて行きたいと。